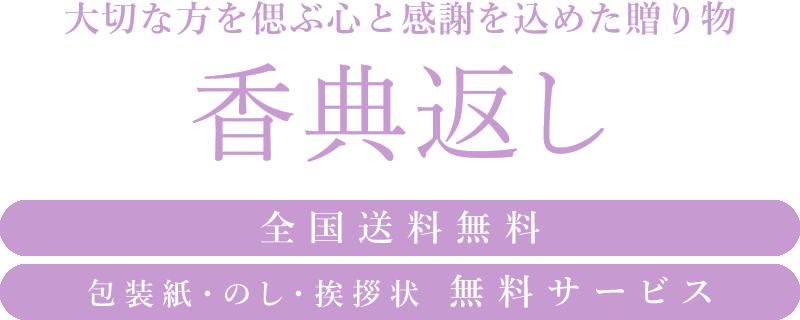香典返しは「のし」じゃなくて掛け紙! 掛け方・書き方など基本を解説
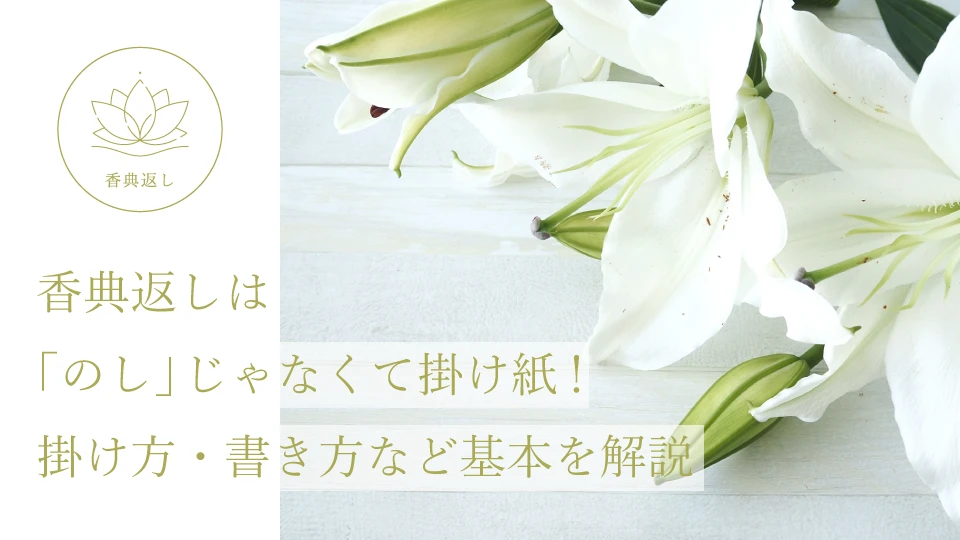
香典返しを贈る際には、「のし」ではなく「掛け紙」を掛けるのがマナーです。今回は香典返しに使用する「掛け紙」について、「のし」との違いを比較しながら掛け方や書き方などの基本知識を解説します。
相手に失礼のないように香典返しを贈るために、ぜひ参考にしてみてください。
香典返しに必要な「掛け紙」と「のし」の違い
「掛け紙」と「のし」は混同されやすいですが、香典返しには「掛け紙」を使用するのがマナーです。ここでは「のし」との違いや、香典返しの「掛け紙」の特徴について詳しく紹介します。
「のし」は縁起物のみに使用する
一般的に「のし」と呼ばれているものは、多くの場合「のし紙」のことを指します。昔、日本では縁起物の鮑(あわび)を贈り物に添える習慣がありました。そのとき使われていた、長く伸ばし干した鮑のことを「熨斗鮑(のしあわび)」と言い、現在では贈り物の際にのしあわびが印刷された紙を掛けるのが一般的です。こののしあわびと水引が印刷された紙のことを「のし紙」と言い、一般的には「のし」と呼ばれます。
のしあわびは縁起物なので、「のし」は慶事である結婚祝いや出産祝い、お中元やお歳暮などの贈り物に添えられます。贈り物に掛ける紙はすべて「のし」と勘違いしている人もいますが、「のし」はあくまでも慶事で使用するもので、弔事の場合は使用しません。
弔事では水引きのみの「掛け紙」を使用する
弔事の贈り物には、のしあわびが印刷されていない「掛け紙」を使用します。掛け紙には水引のみが印刷されていますが、なかには蓮の絵が印刷されているものもあります。蓮の絵がある掛け紙は仏式のみに使用されるもので、仏式の香典返しの場合は蓮の絵が入ったものを選びましょう。それ以外の場合は、水引のみのものを選びます。
香典返しの水引きは「結び切り」
香典返しの掛け紙は、「結び切り」の水引が印刷されたものを選びましょう。結び切りは一度結んだら引っ張ってもほどけない結び方であることから、「繰り返さない」という意味が込められています。弔事は一度きりであってほしい出来事なので、水引は結び切りを使用しましょう。
結び切りとは、具体的には「本結び」のことを指します。また、同じような意味合いで、ほどけにくい結び方である「あわじ結び」が用いられることもあります。「本結び」や「あわじ結び」は弔事のほかにも繰り返すと良くないとされる快気祝いや、結婚祝いなどの慶事の「のし」にも使用できる結び方です。
反対に、「蝶結び」の水引は香典返しには使えません。蝶結びは簡単にほどけて何度でも結ぶことが可能であることから、何度繰り返しても良いとされる合格祝いなどに使用されます。
香典返しの水引きの色は「黒白」または「黄白」
香典返しの水引の色は、宗教を問わず全国的に「黒白」が使用されるのが一般的です。ただし、関西地方など一部の地域やキリスト教、神道では「黄白」の水引が使われることもあります。地域や宗教によって異なるため、親族などの詳しい人に確認してから掛け紙を選ぶようにしましょう。
香典返しでの「掛け紙」の書き方
香典返しでの「掛け紙」は、書き方にも決まりがあります。ここでは「掛け紙」の表書きや名前の書き方について紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
文字(墨)の色は贈る時期によって変える
香典返しでは、忌明けの前後で使用する文字の色を変える場合があります。基本的には四十九日法要までは薄墨で、忌明け後には濃い墨でよいとされています。香典返しは忌明けに贈るのが一般的なので、本来なら濃い墨で問題ありません。しかし、現在では時期に関係なく薄墨を使用するケースもあるため、実際にはどちらを使用しても問題ない場合が多いです。
どちらの色にしてもサインペンやボールペンなどを使用するのは失礼にあたるので、必ず筆や筆ペンなどを使って筆文字で書くようにしましょう。
表書きは「志」が一般的
香典返しの「掛け紙」では、水引の上部の表書きには「志(こころざし)」と書くのが一般的です。「志」には「気持ち」という意味があり、「気持ちばかりのお返し」という意味合いで使われることから、地域や宗教を問わず使用することが可能です。ただし、地域や宗教によっては「志」以外のものが使われる場合もあります。
例えばキリスト教式や神式の場合は「偲び草」、関西や西日本、北陸地方などでは「満中陰志」、中国地方や四国地方、九州地方などでは「茶の子」と書かれる場合もあります。どの書き方にするかは、親族の詳しい人に確認するのが良いでしょう。
また、「志」は地域や宗教を問わず使用できる反面、似た言葉である「寸志」を使用しないように気をつけましょう。「寸志」は目上の立場の人が目下の人へ贈る際に使用する言葉なので、香典返しで使用してしまうと相手に対して失礼にあたります。言葉の意味を正しく理解して表書きに使うようにしましょう。
水引きの下の名前は「喪家の姓」
水引の下部には、「喪家の姓」を書くのが一般的です。基本的には喪家の姓のみ、もしくは喪家の姓に「家」をつけて書きます。また、喪主のフルネームを書く場合もあります。
嫁いだ娘が喪主となる際には娘の新しい姓を書く場合もありますが、受け取る側が分かりやすいように、「旧姓と新姓で連名にする」「旧姓で○○家と記載する」「故人との関係性や続柄も記載する」のいずれかの方法をとるのが一般的です。また、嫁いだ娘の婿が喪主になる際には、故人の姓で「○○家」とする場合が多いです。
香典返しには必ず名前を記載するのがマナーなので、名前を記載しないで贈ることはしません。必ず贈る側の名前を記載するようにしましょう。

香典返しの「掛け紙」の掛け方
「掛け紙」の掛け方には「内掛け」と「外掛け」の2種類があり、一般的に内掛けが良いと認識されている場合が多いです。しかし、なかには外掛けが良いとされる地域もあり、一概にどちらが良いとは言い切れません。
ここでは香典返しの「掛け紙」の掛け方について、それぞれの与える印象の違いなどを解説します。
香典返しは「内掛け」「外掛け」どちらの説もある
香典返しの「掛け紙」は、「内掛け」と「外掛け」の2つの掛け方があります。品物に「掛け紙」をしてから包装する方法が「内掛け」、品物を包装してから「掛け紙」をする方法が「外掛け」です。
香典返しを贈る際に、「内掛け」と「外掛け」のどちらを選べば良いのか悩むこともあるでしょう。どちらかが絶対にタブーということはないので、それぞれの掛け方の印象やメリットを理解したうえで状況に応じて使い分けられると良いでしょう。
「内掛け」を選ぶメリット
「内掛け」を選ぶメリットは、控えめな雰囲気を出せる点や、郵送の際に汚れない点が挙げられます。「掛け紙」を包装の内側に掛けた場合、包装した状態では「掛け紙」が見えないので、弔事にふさわしい控えめな印象を与えられるでしょう。
また、「内掛け」にすることで、郵送する際も掛け紙が汚れたり破れたりするのを防いでくれます。そのため、一般的には香典返しを郵送する場合は「内掛け」にすることが多いです。
「外掛け」を選ぶメリット
「外掛け」を選ぶメリットは、相手に気持ちが伝わりやすい点が挙げられます。包装の外側に「掛け紙」をするため、香典返しを渡した際に一目で表書きや名前を確認できます。そのため、香典返しを持参して相手に直接渡す場合には「外掛け」にすることが多いです。
また、地域によっては「外掛け」が主流の場合もあるので、「掛け紙」を掛ける前に確認しておきましょう。
香典返しの「掛け紙」のポイント
ここでは香典返しの「掛け紙」について、あらかじめ知っておきたい内容を紹介します。贈る相手に失礼のないように、ぜひ確認しておきましょう。
地域や親族のしきたりを確認しておく
弔事における風習は、地域によって大きく異なる場合があります。また、親族によってもそれぞれのしきたりが存在する場合もあるでしょう。現在では一般的に、昔よりも弔事のマナーについては寛容になりつつあります。しかし、風習やしきたりをまったく気にしないで香典返しを贈ってしまうと、場合によっては失礼にあたることもあるので注意が必要です。
香典返しを贈る前に、弔事について詳しい親族に風習やしきたりについてある程度確認しておきましょう。
カタログギフト、商品券にも掛ける
香典返しの品物に「掛け紙」を掛けるのはマナーですが、カタログギフトや商品券などを贈る場合にも「掛け紙」は必要です。基本的に香典返しを贈る際にはどんなものでも「掛け紙」を掛けるようにしましょう。
また、「内掛け」でも「外掛け」でも、包装紙は弔事にふさわしい落ち着いたデザインを選ぶようにしましょう。品物の種類に関わらず、華やかな色味やポップな柄物の包装紙は慶事を連想させてしまい失礼にあたります。香典返しでは薄紫や薄水色、銀などの落ち着いた色味や、菊や雲などの控えめな柄を選ぶようにしましょう。
香典返しの贈り物には、「のし」ではなく「掛け紙」を掛けるのがマナーです。「掛け紙」は「黒白」または「黄白」の結び切りの水引が印刷されたものを使い、一般的に表書きには「志」、下部には「喪家の姓」を書きます。
郵送の場合は「内掛け」、手渡しの場合は「外掛け」とするのが基本ですが、地域や親族のしきたりを確認してから用意するようにしましょう。
香典返しの品物を用意するなら、マイプレシャスのカタログギフトがおすすめです。ラッピングや掛け紙が無料で、お礼状もセットで贈れるため、相手に対して失礼となることなく安心して香典返しを贈れます。
香典返しを選ぶ際には、ぜひマイプレシャスのカタログギフトをご活用ください。
マイプレシャス公式オンラインストアでは、香典返し向けのカタログギフトもご用意しております。
ぜひ選択肢のひとつに加えてみませんか?