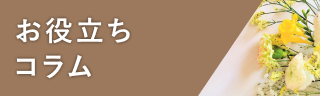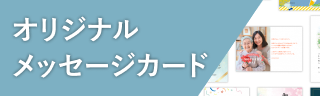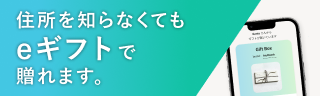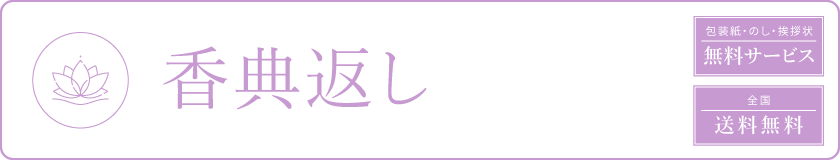香典返し「志」 と「満中陰志」とは? 書き方や選び方
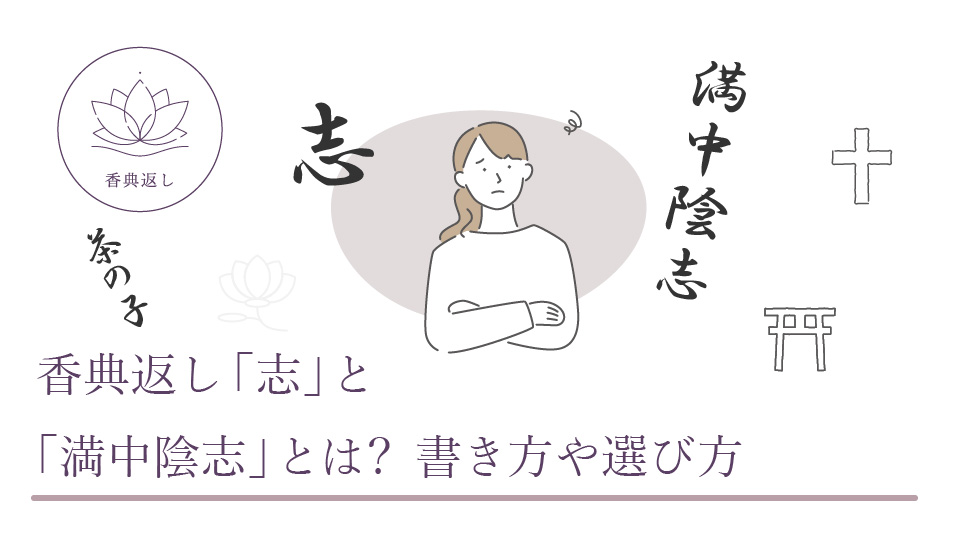
香典返しを贈る際は、表書きに「志(こころざし)」や「満中陰志(まんちゅういんし)」といった言葉を書いて贈ります。地域によって、この表書きに書く言葉が異なります。今回は、香典返しを贈る際の表書きに書く言葉の違いについて、ご紹介します。
関東と関西で違う香典返しの呼び方
香典返しには、のし紙を掛け、そこに表書きを書いて贈るのがマナーです。その表書きに記す言葉でよく目にするのが、「志(こころざし)」です。これには、「気持ち」という意味があり、お香典のお礼ということで、「志」と書かれています。おもに、東日本や四国、九州地方で書かれることの多い言葉です。また、「志」は仏式以外にも、神道など、宗教を問わず、用いることができます。「志」以外にも、関西など、西日本で多く見られるのが、「満中陰志(まんちゅういんし)」や「粗供養(そくよう)」です。また、中国、四国、九州地方の一部の地域では、「茶の子(ちゃのこ)」という言葉も用いられています。
このように、地域によって、表書きに書かれる言葉はさまざまあります。どの言葉も同様に、香典返しで用いられる言葉なので、それぞれお住まいの地域や信仰する宗教の慣習にならって、使い分けましょう。
「満中陰志(まんちゅういんし)」という言葉の意味
仏教では、人が亡くなってから四十九日の間を「中陰(ちゅういん)」と言い、この間、7日ごとに忌中法要が行なわれます。そして、四十九日の日を「満中陰(まんちゅういん)」と言い、忌明けを意味します。「満中陰」には、忌明け法要が行なわれ、これ以降1カ月程度を目安に、お香典をくださった方へ香典返しを贈ります。関西地方などでは、この香典返しを「満中陰志」と言います。
「茶の子(ちゃのこ)」という言葉の意味
「茶の子」には本来、お茶請けや茶菓子という意味があります。中国、四国、九州地方の一部地域では、香典返しや仏事の際に配られる返礼品のことを「茶の子」と言います。その表書きにも「茶の子」と書いて、贈ります。
関東と関西で違う、水引の色
香典返しに限らず、お中元やお歳暮などの贈答品を贈る際は、品物にのし紙をし、その上に水引を掛けます。この水引は、用途によって、結び方や色が異なります。慶事では、紅白の花結びや鮑結びが一般的で、弔事では、黒白の結び切りが用いられることが多いです。また、水引の色には、地域や信仰する宗教によって違いがあります。弔事でよく目にする、黒白の水引は、全国的に広く用いられていますが、特に関東地方で多く見られています。黒白のほかにも、黄白の水引があり、関西地方で多く見られています。
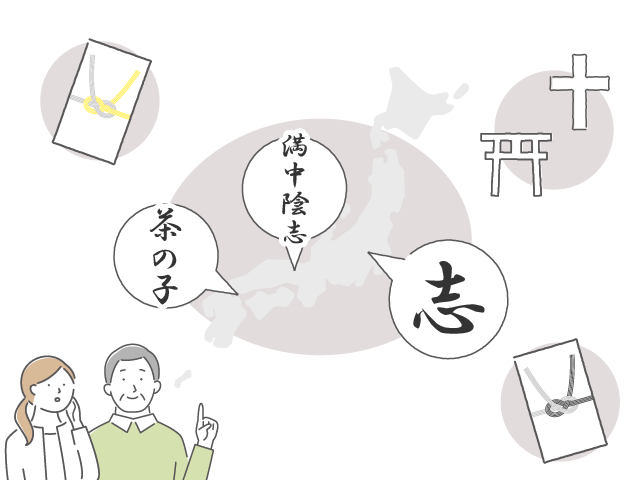
慣習に合ったものを選ぶ際に気をつけること
地域や宗教によって、表書きや水引の色が異なります。香典返しを贈る際は、慣習にならって贈りましょう。
お寺や地元の菓子店に聞く
忌中は、突然の別れをゆっくりと惜しむ間もないほど目まぐるしく、さまざまな行事やその準備に追われます。その中で、分からないことがあって悩んでしまったときは、葬儀などで読経をお願いするお寺や葬祭店に聞くのがおすすめです。また、香典返しの表書きなどで、贈答品を贈る際のことで分からないことがある場合は、茶菓子を多く取り扱っている地元の菓子店で、購入の際に聞いてみるのもよいかもしれません。
迷ったら「志」と書く
地域によって、表書きに書く言葉はさまざまあるため、自分の地域では、何と書いてよいか分からなくなってしまったとき、「志」と書いておくとよいでしょう。「志」は、地域や宗教を問わず、表書きで広く用いられている言葉なので、迷ったら「志」と書くのが、無難でしょう。
香典返しを贈るのにも、その地域や宗教によって、さまざまな慣習が関わってきます。分からないことがあったら、詳しい方に聞くなどして、対処しましょう。
マイプレシャス公式オンラインストアでは、香典返し向けのカタログギフトもご用意しております。
ぜひ選択肢のひとつに加えてみませんか?