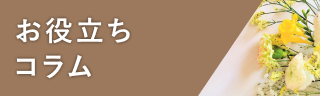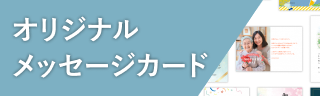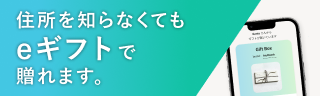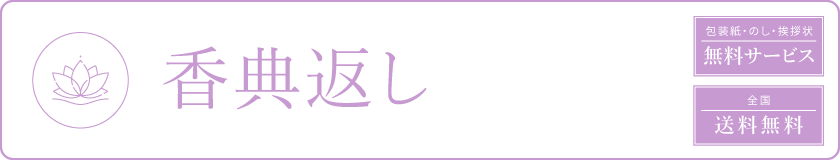香典返しが不要なケースと不要と言われた場合の対処法
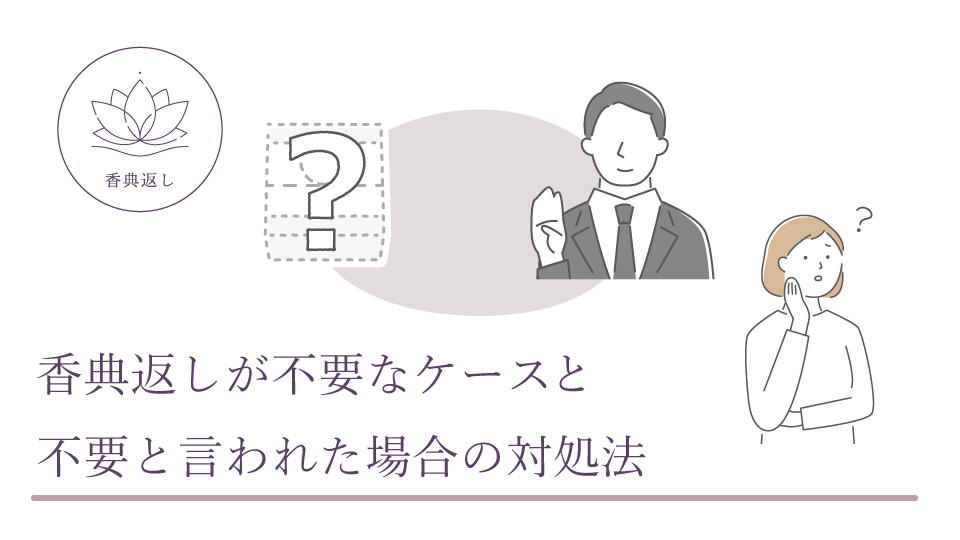
お香典を頂いた方に贈る香典返しですが、なかには、香典返しを辞退されたり、香典返しを贈らないケースもあります。今回は、香典返しを贈らなくてもよいケースや、その場合の対応について、ご紹介します。
香典返しを送らなくてもよいケース
基本的に、香典返しとは、お香典を頂いた方に、そのお礼として贈るものです。ただ、例外として、お香典を受け取っても、香典返しが不要なケースがあります。では、香典返しが不要なケースとは、どんなケースなのでしょうか。
受け取り辞退と言われたとき
お香典をくださる方の中には、香典返しを辞退される参列者もいます。もし、香典返しの辞退の申し出があった場合は、お香典とそのお気持ちだけを受け取って、香典返しを贈らなくてもよいでしょう。どうしても、お礼の気持ちを示したいという場合は、お中元やお歳暮など、香典返しとは別の機会に贈るのがよいでしょう。
また、お手紙や、親しい間柄であれば電話などで連絡するのもよいかもしれません。
受取手のタイミングが悪いとき
香典返しは、四十九日を過ぎた忌明けに贈る場合が多いです。ただ、香典返しを受け取る方の中には、その忌明けのタイミングに、結婚式や新居の竣工などのお祝い事が重なるケースがあります。そのタイミングで、不祝儀に際した贈り物である香典返しを贈るのは避けたほうがよいので、後日、日をあらためて贈りましょう。配送で香典返しを贈る場合は、日時指定のサービスを利用するなどして、荷物が届く日を調整するとよいでしょう。香典返しを受け取る相手が、親しい間柄の人であれば、香典返しを配送で贈ったことを電話やメールなどで、事前に伝えておくのもよいかもしれません。
勤務先都合で受け取れない場合
勤務先の規則で香典返しの受け取りが禁止されている場合があります。お返しをしないのは「失礼になるのでは」というこちらの思いを押し付けてしまっては、かえって相手を困らせてしまうことになります。
では、勤務先の都合で香典返しを辞退された方にはどのような対応をするべきなのでしょうか。できれば直接会ってお礼を伝えるのがベストですが、それが難しい場合には、四十九日の法要後にお礼状をお送りするのが一般的です。その際には、故人が生前お世話になったことに対するお礼と、略式でお礼を述べることに対するお詫びも添えましょう。
香典返しを贈らない場合にはどうするべき?
香典返しを辞退された場合や、贈れない場合に、「お香典を頂いたのに、お返しをしていない」と、不安に思ったり、感謝の気持ちを伝えたいと思う方もいるのではないでしょうか。基本的に、香典返しを辞退される方には、贈るとかえって迷惑になってしまう場合もあるので、香典返しを辞退された場合には無理して贈らないほうが望ましいでしょう。
もし香典返しを贈らない場合でも、お中元やお歳暮など、贈り物をする別の機会に、その折のお礼を一緒に伝えるなどの方法もあります。また、お礼状で感謝の気持ちを伝えるのもよいでしょう。お礼状には、お香典を頂いたお礼と、法要などの忌中行事が無事に済んだことの報告などをしたためて、送りましょう。

香典返しを辞退された場合のお礼状の書き方
香典返しを辞退された方には、四十九日の法要が無事に済んだ報告を兼ねてお礼状を送りましょう。その場合、拝啓や敬具などの「頭語や結語」を使い、句読点を打たないことがマナーです。お礼状のおもな流れとしては、以下を参考にしましょう。
- 1. 頭語(謹啓)と前文挨拶
- 2. 通夜や葬儀への参列と香典に対するお礼
- 3. 四十九日法要を無事に終えたことの報告
- 4. 略式でのお礼となることに対するお詫び
- 5. 結語(敬具または敬白)
- 6. 日付(四十九日の法要を行なった日)
- 7. 喪主の名前
イレギュラーな対応になりますが、香典返しの辞退は、ご参列いただいた方のお気持ちや、ご都合によって起こることです。忙しい時間の合間を縫って、お通夜や葬儀にご参列くださったことなどへの感謝の気持ち忘れずに、状況に合わせて、柔軟に対応しましょう。
マイプレシャス公式オンラインストアでは、香典返し向けのカタログギフトもご用意しております。
ぜひ選択肢のひとつに加えてみませんか?